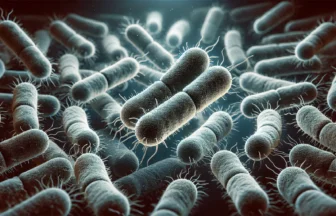近年、世界的に注目されている衛生管理手法の一つに「HACCP(ハサップ)」があります。
食品業界だけでなく、介護施設や学校給食など、さまざまな場所で導入が進み、食中毒の予防や品質向上に役立っているのです。
本記事では、「HACCPとは?」という疑問に応えるため、定義や特徴、導入方法、そしてメリットについてわかりやすく解説します。
HACCPの基本:定義と背景
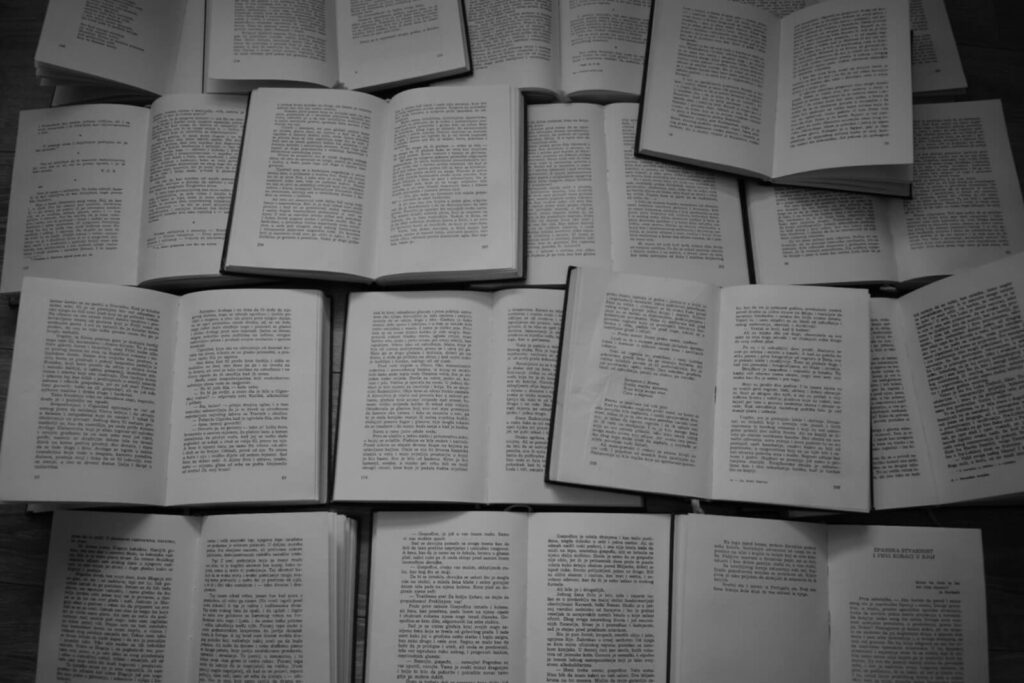
HACCPとは?
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析と重要管理点)とは、食品の製造・調理工程における危害要因を事前に分析し、その管理が特に重要な工程(重要管理点)を監視する手法のことです。
「完成品を検査して不良を取り除く」従来の方法とは異なり、「工程ごとに危害を予測し、未然に防ぐ」という考え方が特徴です。
HACCPの歴史
HACCPはもともと、アメリカのNASAが宇宙食の安全性を確保するために開発したシステムに由来します。
1960年代に宇宙飛行士へ供給される食品で、絶対に食中毒があってはならないという強い要請から、危害を事前に排除する仕組みが考案されたのです。
その後、国際的に食品安全基準の整備が進むにつれ、HACCPは世界中の食品業界で採用されるようになりました。
HACCPの特徴と構成要素
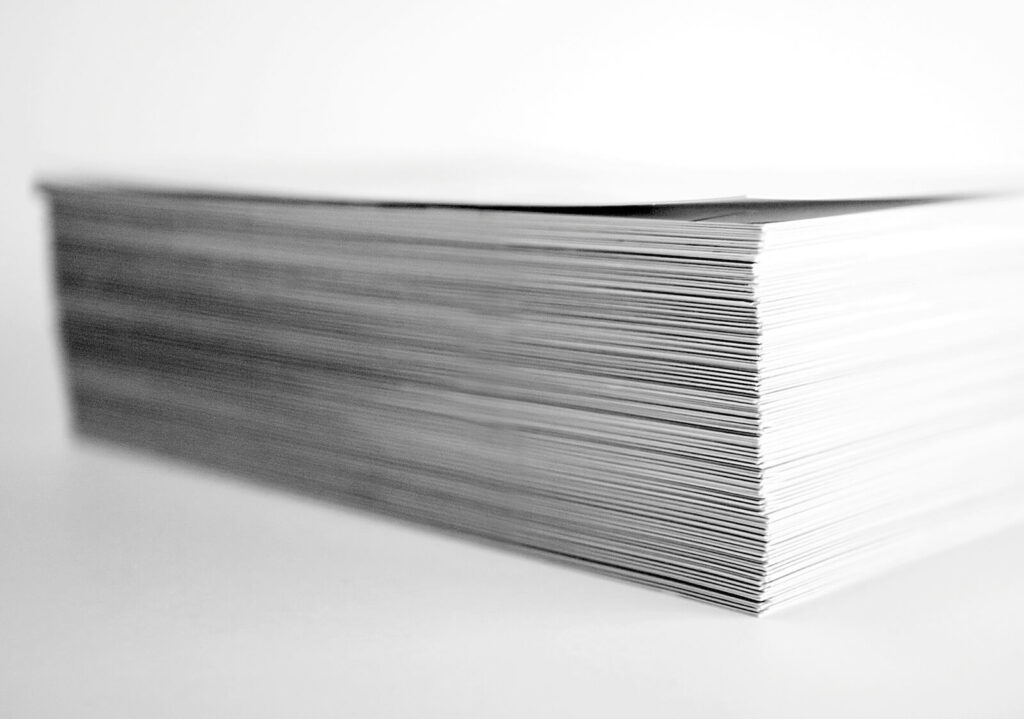
従来の管理手法との違い
従来の食品衛生管理では、完成品の一部を検査して安全を確認し、不良品が見つかれば廃棄する方法が一般的でした。
一方、HACCPでは、製造・調理のプロセス全体を分析し、食中毒や異物混入などの危害が起こりうるポイントを特定。そのポイントにおいて、適切な管理基準を設定し、監視・記録を行うことで、危害要因を排除・低減します。
HACCPの7原則
HACCPは、国際機関(コーデックス委員会など)が提唱する7つの原則によって構成されています。以下に、その概要を示します。
| 原則番号 | 内容 |
| 1. 危害要因分析 | 工程内で発生し得る危害(食中毒菌、物理的異物など)を洗い出し、発生要因を分析する |
| 2. 重要管理点 (CCP) の設定 | 危害を防止するために特に管理が必要なポイント(温度、加熱時間など)を決める |
| 3. 管理基準(Critical Limit:CL) の設定 | CCPで守るべき具体的な基準値(温度75℃以上で1分加熱など)を設定する |
| 4. CCPのモニタリング | 管理基準が守られているかを監視し、記録を残す |
| 5. 是正措置 | 管理基準を逸脱した場合に、どのように修正・廃棄するかなどの対処方法を決める |
| 6. 検証 | 全体のシステムが効果的に機能しているかを定期的に確認・評価する |
| 7. 文書化と記録の保持 | HACCP計画やモニタリング結果などを文書化し、後から検証できるように保管する |
HACCP導入の手順

前提条件プログラムの整備
HACCPの効果的な運用には、前提条件プログラム(PRP)の整備が欠かせません。
PRPには、施設の清掃や害虫・ネズミ対策、手洗い設備の充実など、食品衛生管理の基礎的な取り組みが含まれます。
HACCPプランの作成と運用
- 工程表の作成
- 食材の受け入れから出荷までの全工程をリストアップし、フローチャートを作る
- 危害要因分析
- 各工程で発生し得る危害を洗い出し、その原因を特定
- CCP(重要管理点)の設定
- 危害をコントロールできる要の工程に管理基準を設ける
- モニタリング方法の決定
- 温度計測やpH測定など、日常的に監視する仕組みを確立
- 記録と是正措置
- 毎日の測定結果を文書化し、基準を逸脱した場合の対応方法を決める
- 検証・見直し
- システム全体が適切に機能しているか、定期的にチェックしアップデートする
HACCP導入のメリットと注意点

主なメリット
| メリット | 具体例 |
| 食中毒リスクの低減 | – 危害要因を未然に発見し、早期に対処できる |
| 品質向上と顧客信頼の確保 | – 安全性が保証された食品を提供することでブランド価値が高まり、取引先や消費者からの信頼が向上 |
| トレーサビリティ(追跡可能性)の向上 | – CCPを中心にモニタリングと記録を行うため、問題発生時に原因箇所を特定しやすく迅速に対応できる |
| 作業効率の改善 | – 工程ごとの役割分担が明確になり、無駄や重複作業を削減 |
注意点
- 導入コストと人材育成
- 温度計や記録システムなどの設備投資が必要であり、従業員への教育にも時間とコストがかかる
- 小規模事業者の負担
- 大企業に比べて人員や資金に制約がある小規模事業者にとって、HACCP導入は難易度が高い場合も
- 継続的な運用と見直し
- 一度導入しただけで満足せず、定期的に見直しや改善を行う必要がある
HACCPの義務化と今後の展望

日本では、2021年6月から食品衛生法の改正により、「HACCPに沿った衛生管理」がすべての食品事業者に義務付けられました。
これによって、従来の大企業だけでなく、小規模事業者や個人商店なども何らかの形でHACCPの考え方を取り入れる必要が生じています。
一方で、「コストがかかる」「専門知識が必要」といった課題もあり、行政や専門機関は小規模事業者向けの簡易版HACCPや、無料セミナー、マニュアル提供などの支援を行っています。
将来的には、HACCPによって日本の食品産業全体の衛生水準が底上げされ、国際的な競争力も高まることが期待されています。
HACCPは安全・安心な食品のための必須システム

HACCP(ハサップ)は、危害要因の事前分析と重要管理点の徹底監視によって、食品の安全性を飛躍的に高めることができる仕組みです。
従来の検査・廃棄方式とは異なり、未然にトラブルを防ぐ“プロアクティブ”なアプローチが特徴です。
- 危害要因分析(Hazard Analysis)
- 工程を洗い出し、潜在的な危害を事前に把握する
- 重要管理点(Critical Control Point)
- 危害をコントロールできるステップを特定し、基準を設定
- 記録と検証
- モニタリング結果を残し、定期的にシステムの有効性を検証する
この一連の流れを実践することで、食中毒などの衛生リスクを大幅に減らせるほか、品質向上や顧客満足度アップにもつながります。
日本でも食品衛生法改正により、HACCPがすべての食品事業者に求められるようになりました。大変そうに感じるかもしれませんが、行政や各種支援機関のサポートを活用すれば、着実に導入が進むでしょう。
「HACCPとは?」と疑問に思っていた方は、ぜひ本記事をきっかけに具体的な導入や運用方法を検討してみてはいかがでしょうか。安全・安心な食品づくりは、消費者との信頼関係を築く大きなカギとなるはずです。