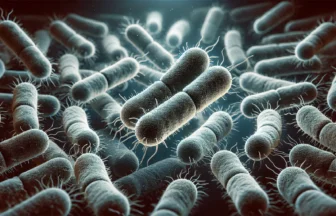大量調理施設では、一度に多くの人に食事を提供するため、食中毒のリスクが高まります。
特に、冬季を中心に流行するノロウイルスによる食中毒は、大人数に一気に感染が広がる可能性があるため注意が必要です。
厚生労働省が提示している「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、このようなウイルス性食中毒を防ぐために、従業員の定期的な健康管理や検便が推奨されています。
本記事では、大量調理施設における検便とノロウイルス対策について、「大量調理施設衛生管理マニュアル」の視点から詳しく解説します。
大量調理施設衛生管理マニュアルとは

大量調理施設衛生管理マニュアルは、学校給食や社員食堂、病院、介護施設など、1回の調理で多数の食事を提供する施設を対象に作成されたガイドラインです。
厚生労働省が提示しており、「食中毒予防の基本原則」を踏まえつつ、以下のようなポイントが強調されています。
- 衛生的な食材取り扱い
- 温度管理と交差汚染防止
- 従業員の健康管理(検便を含む)
- 施設・設備の清掃消毒
- 異物混入防止
中でも従業員の健康管理は非常に重要であり、ノロウイルスの感染拡大を防ぐためにも、定期的な検便や体調確認が必要とされています。
ノロウイルスと大量調理施設の関係
ノロウイルスによる食中毒の発生件数は、特に冬期に集中します。感染力が極めて強く、少量のウイルスでも症状を引き起こすため、大量調理施設でひとたび感染者が出ると、大規模な集団感染に発展しかねません。
そのため、施設全体で予防策を講じることが必須となります。
ノロウイルスとは?

感染経路と特徴
ノロウイルスは、ウイルス性胃腸炎の主な原因の一つです。主な感染経路は以下のとおりです。
- 経口感染(飲食物から)
・ノロウイルスに汚染された食品を摂取する
・ウイルスが付着した手指や調理器具などを介して口に運んでしまう - 接触感染
・感染者の嘔吐物や糞便が付着した場所を触り、その手で口や鼻を触る - 飛沫感染
・嘔吐物の飛沫を吸い込んでしまう
ノロウイルスは、少量の菌量でも発症しやすく、主な症状は嘔吐・下痢・腹痛・発熱などです。
通常は2~3日ほどで回復しますが、高齢者や幼児など免疫力が低い人が感染すると重症化のリスクが高まります。
ノロウイルスに対処する重要性
厚生労働省が公表している食中毒統計によれば、ノロウイルスによる集団感染は毎年繰り返し発生しており、大量調理施設でのクラスター(集団感染)事例も珍しくありません。
こうした背景から、「大量調理施設衛生管理マニュアル」でも特にノロウイルス対策が強調されています。
検便の重要性と実施ポイント

なぜ検便が必要か
大量調理施設で働く従業員がノロウイルスや他の食中毒原因菌を保菌していると、本人に自覚症状がない場合でも食品を通じて他者に感染させてしまう可能性があります。
定期的な検便を行うことで、無症状の保菌者を発見し、速やかに対策を取ることが可能になります。
主な狙い
- 食中毒の未然防止
- 従業員や利用者の安全確保
- 施設の信用保持
検便の実施頻度
大量調理施設衛生管理マニュアルでは、従業員の検便に関して定期的な実施を推奨しています。
具体的な回数は施設や自治体の指導によって異なりますが、通常は年1~2回程度が一般的です。特にノロウイルスが流行しやすい冬場に、追加で検査を実施する施設も増えています。
また、従業員が体調不良を訴えた場合(嘔吐・下痢・発熱など)や、施設内でノロウイルス感染が疑われる事案が発生したときには、臨時で検便を行うケースもあります。
ノロウイルス予防のための衛生管理策

従業員の健康管理
- 検便のほか、出勤前の体調確認
下痢や嘔吐、発熱の症状がある従業員は、調理業務を控えるよう指示することが基本です。 - 手洗いの徹底
ノロウイルスを含めた多くの感染症は、手指衛生を徹底することでかなり防げます。爪や指の間、手首までしっかり洗い、清潔なペーパータオルや乾燥機で乾かしましょう。
食材・調理器具の衛生管理
- 加熱調理の徹底
ノロウイルスは85~90℃で90秒以上の加熱により失活するといわれています。二枚貝(牡蠣など)や加熱不足になりやすい食品は、特に注意が必要です。 - 交差汚染を防ぐ
生の食材を扱った包丁やまな板などは、しっかり洗浄・消毒を行い、専用の調理器具を使うことが望ましいです。
嘔吐物・糞便の処理方法
ノロウイルス感染者が出た場合、嘔吐物や下痢便を適切に処理しなければ、施設内にウイルスが拡散する危険性があります。
塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用し、床や器具を消毒するとともに、使い捨てマスク・手袋を着用して作業にあたることが基本です。
衛生管理策一覧表
以下の表は、大量調理施設でノロウイルスなどの食中毒を防ぐために、特に重点的に取り組むべき衛生管理策をまとめたものです。
| 項目 | 具体的な管理策 |
| 従業員の健康管理 | ・定期的な検便(特にノロウイルス流行期)・出勤前の体調確認(下痢・嘔吐・発熱の有無)・症状がある場合は出勤停止 |
| 手指衛生 | ・こまめな手洗い(調理前後、トイレ使用後、休憩後など)・爪は短く清潔に保つ・清潔なペーパータオルでしっかり乾燥 |
| 食材・調理器具の衛生管理 | ・生食用と加熱用の器具を分ける・包丁やまな板などは使用後すぐ洗浄・消毒・食品の中心温度が85~90℃以上になるよう加熱 |
| 嘔吐物・糞便の処理 | ・使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用・次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒・処理後は手指消毒の徹底 |
| 環境衛生(床・換気設備など) | ・定期的な清掃・消毒・調理室の温度・湿度管理・ゴミ置き場の清掃と害虫・ネズミ対策 |
| 衛生管理の教育・マニュアル整備 | ・新入社員やパート・アルバイトへの衛生教育・マニュアルの定期的見直し・衛生委員会の設置やチェックリストの活用 |
最近の動向と統計

厚生労働省が発表している食中毒統計によると、ノロウイルスによる食中毒の発生件数は毎年のように上位を占めるという報告があります。
特に冬季には、感染力の強いノロウイルスが原因で集団感染が起きやすい傾向にあります。近年では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、手洗いや手指消毒の習慣が普及したこともあり、一部の食中毒発生が減少したとする報告もあります。
しかし、社会活動が戻りつつある現状では、再びノロウイルス感染事例が増加する可能性があり、大量調理施設では引き続き厳格な衛生管理が求められています。
また、厚生労働省や自治体は、食品を扱う事業者に対して「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の推進を呼びかけています。
大量調理施設衛生管理マニュアルもその一環として位置づけられており、検便や施設内の清掃・消毒などを体系的に行うことで、利用者が安心して食事を取れる環境づくりが期待されています。
大量調理施設衛生管理マニュアルを理解して検便やノロウイルス対策を徹底しよう

大量調理施設では、数十人から数百人規模の利用者に一度に食事を提供するため、食中毒の発生は大きな影響を及ぼします。
特に感染力の強いノロウイルスは、冬季を中心に集団感染を引き起こしやすく、徹底した衛生管理と定期的な検便が欠かせません。
そのため、大量調理施設では「衛生管理マニュアル」に基づき、リスクを最小限に抑えるための対策が求められています。
- ポイント1:従業員の定期検便や体調確認を実施する
- ポイント2:手洗いや調理器具の洗浄・消毒など、基本的な衛生管理を徹底
- ポイント3:嘔吐物や下痢便の処理方法をマニュアル化し、感染拡大を防ぐ
これらの対策を怠ると、多数の人が一気に食中毒にかかってしまう可能性が高まります。食の安全を守るためにも、マニュアルに沿った衛生管理を日々継続して実践していきましょう。