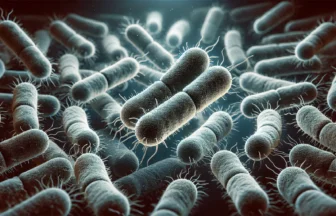温泉や大浴場、加湿器などの水回りを利用する機会は多いですが、これらの環境でレジオネラ菌が増殖すると、思わぬ健康リスクにつながることをご存じでしょうか?
レジオネラ菌は自然界に広く存在し、適切な管理がされていない施設では空気中に微細な水滴(エアロゾル)として拡散し、それを吸入することで感染する可能性があります。
特に、高齢者や免疫力が低下している方にとってはレジオネラ症(レジオネラ肺炎)のリスクが高まり、重症化するケースも報告されています。
本記事では、レジオネラ菌の特徴や感染経路、主な症状、そして具体的な予防策について、最新の情報を交えながら分かりやすく解説します。
レジオネラ菌とは?
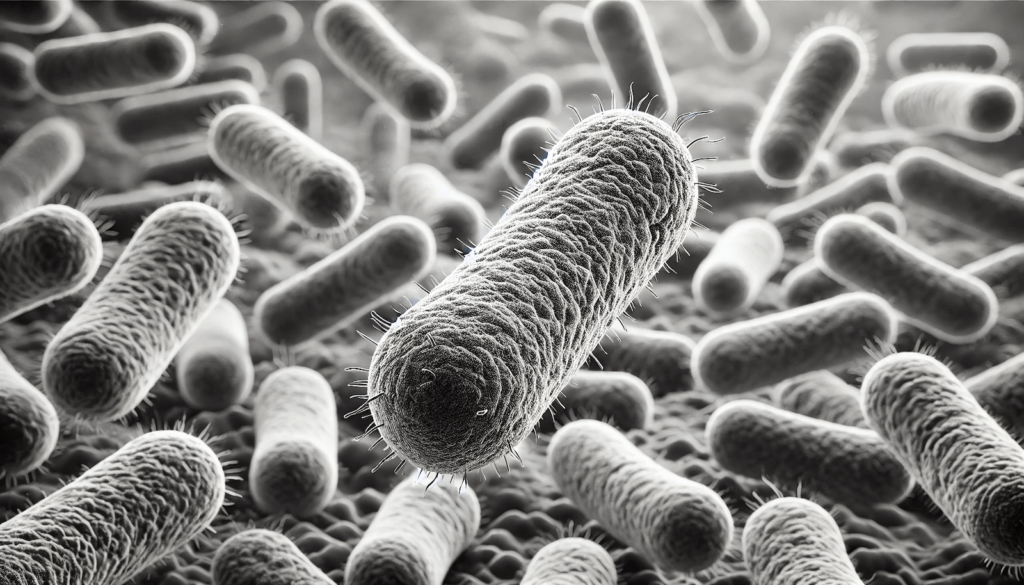
基本的な性質
レジオネラ菌(Legionella pneumophila)は、水中に生息するグラム陰性桿菌(かんきん)の一種です。
比較的高温でも生存可能で、特に20~50℃程度の水温を好んで増殖する特徴があります。
自然界の河川や湖、土壌などにも広く分布しており、そこから人間が利用する給湯設備や空調装置、さらには大規模な循環式浴場などへ侵入し、増殖するケースが指摘されています。
レジオネラ症と集団感染のリスク
レジオネラ菌が原因で引き起こされる感染症は、総称して『レジオネラ症』と呼ばれます。
レジオネラ菌は空気中を浮遊する飛沫(エアロゾル)を介して吸い込まれることで肺に到達し、感染を引き起こす可能性があります。
温泉施設やスーパー銭湯などの循環式浴槽、また冷却塔などの空調設備が原因施設となり、過去には大規模な集団感染が起きた事例も報告されています。
レジオネラ菌による病気の症状の特徴
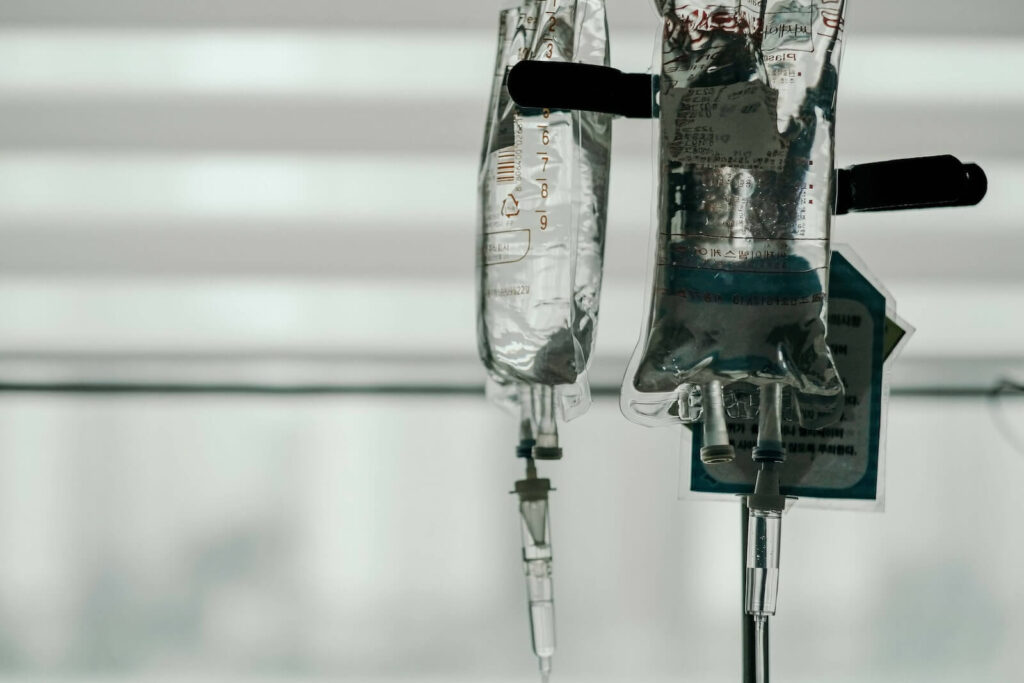
レジオネラ肺炎とポンティアック熱
- レジオネラ肺炎
- 発熱、咳、倦怠感などの一般的な肺炎症状が現れます。進行すると呼吸困難、胸痛を伴うこともあり、重症化すると入院治療が必要になるケースもあります。
- 高齢者や慢性呼吸器疾患、糖尿病など基礎疾患を持つ方は特にリスクが高いとされています。
- ポンティアック熱
- レジオネラ菌感染によるもう一つの症状で、発熱、頭痛、筋肉痛などを引き起こしますが、肺炎の症状は伴いません。
- 比較的軽症で治癒することが多く、重篤化はまれと報告されています。
潜伏期間と診断
レジオネラ肺炎の場合、2~10日程度(多くは5~6日)の潜伏期間を経て症状が現れます。
症状が進行すると、高熱や悪寒、下痢、意識障害など多彩な症状を伴うことがあるため、自己判断せず医療機関を受診することが重要です。
診断には尿中抗原検査や喀痰培養、血液検査などが利用され、適切な治療を受けることで回復が期待できます。
レジオネラ菌の感染経路

吸入(エアロゾル感染)が主なルート
レジオネラ菌は、飛沫(エアロゾル)を介してヒトの肺に入り感染を引き起こすのが特徴です。
具体的な感染源としては、以下のような水を扱う施設・設備が挙げられます。
- 循環式温浴施設(温泉・銭湯・スパ施設など)
- 冷却塔(空調設備の一部)
- シャワー・蛇口(長期間使用されていない場合など)
- 噴水や加湿器(メンテナンス不足の機器)
飲み水を介する経口感染ではなく、あくまで水滴が肺に吸い込まれることで発症する点が大きな特徴です。
そのため、施設でのお湯管理や配管の清掃が不十分だと、レジオネラ菌が繁殖しやすい環境を生み出してしまいます。
人から人への感染はまれ
レジオネラ菌は、基本的に人から人へ感染することはないとされています。これまでの研究でも、ヒト同士の感染例は報告されていません。
しかし、免疫力が低下している方や高齢者が感染すると、重篤化するリスクが高まるため、適切な予防措置を講じることが大切です。
レジオネラ菌による感染を防ぐための対策

一般家庭でできること
- 給湯器やシャワーの定期的な使用
- 長期間放置した配管には菌が繁殖しやすいため、定期的に湯を流すことが予防につながります。
- 浴槽のこまめな清掃
- 入浴後は浴槽の湯を抜き、浴槽表面や排水口まわりを洗浄しておきましょう。
- 温度管理
- レジオネラ菌は20~50℃あたりで増殖しやすい性質があります。家庭用給湯器は60℃以上の設定にし、湯船に浸かる際には適宜お湯を交換するなど、菌の繁殖を抑える工夫が大切です。
施設や事業者での対策
| 対策項目 | 具体的な方法 |
| 循環式温浴施設の管理 | – 浴槽水の塩素濃度や濁度の定期チェック- フィルターや配管の定期的な洗浄・殺菌- 適切な湯温を維持 |
| 冷却塔や空調設備の点検 | – 定期的な清掃と水の交換- バイオフィルム(微生物の塊)の発生防止剤の使用 |
| シャワーヘッドや配管の洗浄 | – シャワーヘッドを定期的に取り外して煮沸消毒や塩素消毒を行う- 使用していない蛇口やシャワーも定期的に流水で洗浄 |
| 加湿器・噴水の管理 | – 加湿器の水タンクをこまめに洗浄- 噴水の水を定期的に交換し、苔や汚れがたまらないようにする |
レジオネラ菌に感染した場合の対応

主な治療方法
レジオネラ症(レジオネラ肺炎)は、マクロライド系やニューキノロン系など、特定の抗生物質に感受性があるとされています。早期発見と適切な抗菌薬の使用により、多くの患者は回復が見込まれます。
ただし、高齢者や基礎疾患を持つ方は重症化のリスクが高いため、症状が疑わしい場合は速やかに医療機関を受診してください。
予後と再発防止
適切な治療を受ければ改善が期待できますが、免疫力が低い方は経過観察が必要です。
また、治癒した後も同じ施設や環境を利用し続けると再び感染する可能性がないとはいえません。
施設管理者がしっかりと設備を点検し、衛生管理に注力することが再発防止につながります。
レジオネラ菌に関する最近のトピックと統計データ

厚生労働省が公表している感染症発生動向によると、レジオネラ症の報告数は年々増加している傾向にあります。高齢化社会の進展や入浴施設の需要拡大に伴い、感染リスクが高まっているとも考えられます。
さらに、家庭用の循環式風呂やコンパクトなジャグジーバスなどが普及し、自宅でもレジオネラ菌に曝露する可能性が増えているのです。
一方で、定期的な清掃や消毒、適切な温度管理の徹底によって、多くの事例は予防可能とされています。自治体や保健所も、レジオネラ菌の監視を強化し、施設に対して適切な指導を行う動きが広がっています。
レジオネラ菌による病気の症状を知り、安全な水環境を守ろう

レジオネラ菌は、普段私たちが利用する浴場や空調設備、水回りなど、さまざまな場所に潜んでいる可能性があります。
感染すると肺炎などの重い症状を引き起こすことがあり、特に高齢者や免疫力が低下している方にとっては大きなリスクとなります。だからこそ、施設管理者や家庭での衛生管理が重要になります。
- 給湯や循環設備を定期的に清掃し、湯温と塩素濃度を適切に保つ
- 長期間使っていないシャワーや蛇口は、こまめに流水を行う
- 発熱や咳、呼吸苦などレジオネラ菌 症状が疑われる場合は早めに受診する
こうした対策を徹底することで、レジオネラ菌による感染リスクを大きく減らせます。
安全な水環境を維持し、快適な入浴・生活を続けるためにも、ぜひ本記事を参考に日常からの取り組みを見直してみてください。