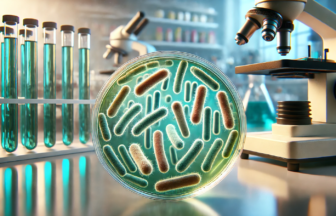食品の安全管理が重要視される中、サルモネラ菌による食中毒リスクが改めて注目されています。鶏卵や鶏肉が主な感染源として知られていますが、実は意外なところから感染が広がることも。
本記事では、サルモネラ菌の基本情報や予防策、検査・治療方法について詳しく解説します。
サルモネラ菌とは?
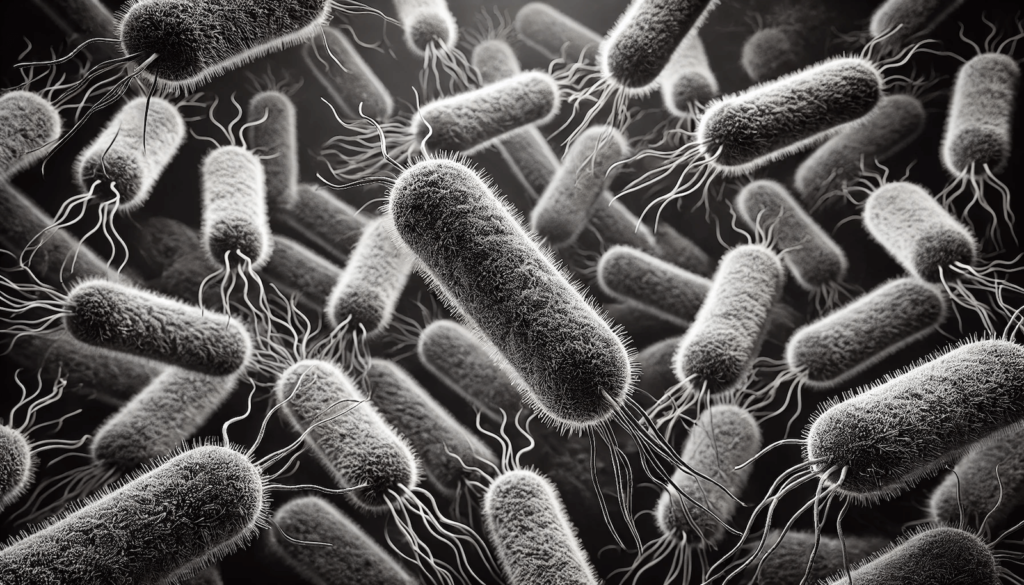
基本的な性質
サルモネラ菌には多くの種類があり、腸チフスやパラチフスを引き起こすチフス性サルモネラ(Salmonella Typhi、Salmonella Paratyphi)と、食中毒の原因となる非チフス性サルモネラに分類されます。
食中毒との関係
サルモネラ菌は食品を通じてヒトの体内に入り、腸管で炎症を引き起こし、胃腸炎の症状を発症させます。
代表的な食中毒原因菌の一つであり、高温多湿の夏場に特にリスクが高まりますが、食品の取り扱いや保管状態によっては、季節を問わず発生する可能性があります。
サルモネラ菌による食中毒の原因と症状

主な原因食品
サルモネラ菌の主な感染源は、食品(特に動物性食材)ですが、人やペットとの接触、不衛生な水や環境からの感染も報告されています。
感染源となり得る、代表的な食品についてご紹介します。
- 鶏肉・卵
- 十分に火が通っていない鶏肉料理や、生・半熟卵を使ったメニューなどから感染する事例が多いです。
- 牛肉・豚肉
- 鶏肉ほど頻度は高くありませんが、内臓や生食用の部位などから菌が検出される場合もあります。
- 加工食品(マヨネーズ、アイスクリームなど)
- 卵を原材料に含む加工食品で、製造工程の温度管理が不十分な場合、菌が増殖しやすいです。
また、調理器具や手指がサルモネラ菌に汚染されていると、他の食品に二次汚染を引き起こす危険性があります。
潜伏期間と症状
サルモネラ菌を摂取してから症状が出るまでの潜伏期間は、おおむね6~48時間とされています。主な症状としては、以下のようなものがあります。
- 下痢
- 腹痛
- 発熱(38℃前後が多い)
- 嘔吐(個人差あり)
通常、1~3日ほどで回復するケースが多いですが、高齢者や乳幼児、基礎疾患のある方は重症化するリスクが高まります。その場合は早めの医療機関受診が推奨されます。
サルモネラ菌 食中毒の予防策

衛生管理の基本:つけない・ふやさない・やっつける
食中毒対策の基本である「つけない」「ふやさない」「やっつける」は、サルモネラ菌にも有効です。
- つけない
- 生肉や生卵を扱う際は、まな板や包丁、トングなどを他の食品と分けて使用
- 手洗いを徹底し、菌を別の食材や調理器具へ移さない
- ふやさない
- 食品は冷蔵または冷凍し、常温で長時間放置しない
- 消費期限や賞味期限を守り、庫内温度の管理を行う
- やっつける
- 中心温度75℃以上で1分以上の加熱を目標
- 卵や鶏肉を使った料理は特に火通しを入念に行う
対策一覧表
サルモネラ菌 食中毒を予防するための具体的な対策を、下表にまとめました。
| 対策項目 | 具体的な方法 |
| 購入・保管 | – 卵や肉は消費期限を確認し、すぐに冷蔵庫へ- 冷蔵庫の温度は10℃以下、理想的には5℃以下に保つ |
| 調理器具の使い分け | – 生肉と野菜、加熱済み食品でまな板や包丁を分ける- 同じ器具を使う場合は洗剤と熱湯でしっかり洗浄・消毒 |
| 十分な加熱 | – 鶏肉や卵などは中心温度75℃以上を目指す- 大量調理の場合は特に加熱ムラに注意 |
| 手洗いの徹底 | – 調理前やトイレ使用後、生肉を扱った後には石けんで手洗い- 爪の間、指先、手首もしっかり洗浄 |
| 二次汚染の防止 | – 使用後の調理器具はすぐに洗い、清潔なふきんで拭く- 生ゴミや汁が出る食材は密閉し、室温に長時間置かない |
| 残った食品の再加熱 | – 食べきれなかった料理は冷蔵保存し、再度食べる時は十分に温める- 保存期間が長くなる場合は冷凍保存を検討 |
サルモネラ感染の診断と治療

検便検査によるサルモネラ感染者の発見
サルモネラ菌に感染しているかどうかを正確に調べるためには、検便(便の培養検査)が標準的な方法ですが、近年ではPCR検査も活用されており、迅速に結果を得ることが可能です。
- 食品関連の事業者では、定期的に従業員の検便を実施することで、無症状の保菌者を早期に発見し、集団感染を防ぐ対策が広く行われています。
- 一般の方でも、サルモネラ感染が疑われる症状がある場合は、医師の判断により検便を行い、確定診断を下す流れが一般的です。
治療の基本
サルモネラ菌による食中毒の多くは、軽症の場合は自然に回復することが多いとされています。しかし、嘔吐や下痢による脱水症状に注意が必要なので、経口補水液などでの水分補給が大切です。
症状が重くなったり、高熱が続く場合には、医療機関での治療が必要です。医師の判断により、抗生物質の投与や点滴などが行われる場合もあります。
最近の動向と統計
厚生労働省が毎年公表する食中毒統計によると、サルモネラ菌による食中毒は比較的古くからある一方、依然として発生件数の上位に含まれる菌の一つです。
近年では、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて衛生意識が高まり、一時的に食中毒件数が減少したという報告もありますが、経済活動や外食の活発化に伴い、再びサルモネラ菌による食中毒の増加が懸念されています。
また、HACCP(ハサップ)の導入や検便検査など、予防策の徹底によってサルモネラ感染リスクを下げる努力が広がっているのも現状です。
サルモネラ菌 食中毒を防ぐために

サルモネラ菌は、鶏肉や卵などの身近な食材から感染しやすく、下痢や腹痛、発熱などの症状を引き起こす代表的な食中毒原因菌です。
中心温度75℃以上での加熱や、調理器具の分別使用、手洗いといった基本的な対策を実践することで、大部分のリスクは低減できます。
さらに、検便検査を行うことで感染者を早期発見でき、食品関連の事業所などでは定期的な検査が食中毒の集団発生を防ぐうえでも有効です。もしサルモネラ感染が疑われる症状が出た場合は、脱水予防を心掛けつつ、早めに医療機関で診察を受けましょう。
定期的な衛生チェックと検便検査を通じて、私たちの食卓を安全で安心なものに保つことができるのです。